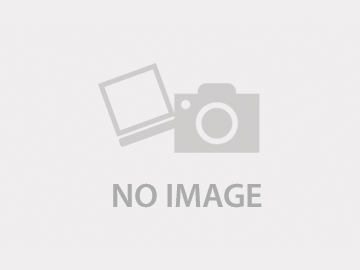秋の七草という草花は初秋の9月に美しさを放つ、草花として鑑賞されてきました。
その歴史は奈良時代である8世紀初頭から引き継がれおり、非常に長く続いているのです。
その始まりは、”山上憶良”が数ある花の中から秋を代表する七種の草花を歌に残したことで生まれたと言われています。
このコラムでは、春の七草の歌についてのあれこれをご紹介致します。
万葉集の歌
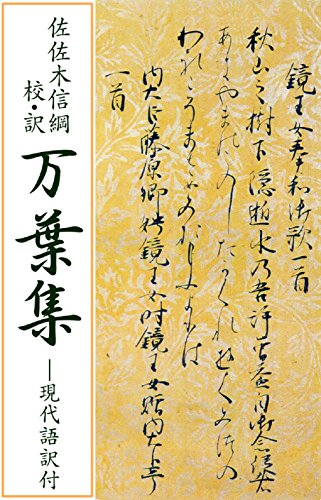
まずは、その歌は次になります。
巻8の1537
「萩の花 尾花葛花(くずはな) なでしこの花 おみなえし また 藤袴(ふじばかま) 朝顔の花」
巻8の1538
二首一組になっており、二種目の「朝顔」の花は「桔梗」であるとされていますが、この話は後ほど解説致します。
それぞれの花の画像、特徴については次のコラムをご参照下さい。
この歌はとてもシンプルで、秋の野に咲いている花を指折り数えてみれば、七種類の花があり、それは「萩(おぎ)、尾花(おばな、ススキのこと)、葛(くず)、撫子(なでしこの)、女郎花(おみなえし)、藤袴(ふじばかま)、桔梗(ききよう)」の七つの草花であることを詠っているのです。
この歌がなんで注目をされて「秋の七草」と呼ばれ始め、ここに登場する七つの草花が初秋の代表的な鑑賞花の7つに選ばれる存在になったのか?この歌だけではピンとこないでしょう。
朝顔がなぜ桔梗なの?

七つの草花のうち一番最後にある「朝顔の花」は桔梗(ききょう)であるとされています。
この説の正しいとされたのは、植物学者の”牧野富太郎博士”{1862年(文久2年)~1957年(昭和32年)}の説によるものです。
”山上憶良”が詠った「朝顔」は、朝顔(あさがお)、昼顔(ひるがお)、木槿(むくげ)とも、桔梗(ききょう)の4つの説がありましたが、桔梗であるというのが有力な説です。
牧野博士が桔梗であるという言っている説の根拠は次のものになります。
牧野博士説の根拠
(2)万葉集の別の歌の中には「朝顔は夕方に咲くのが見事」というものがあり、現代の朝顔とは特徴が異なる。
(3)木槿(むくげ)については、中国のから入ってきた草花であり、自然に自生しているとは考えられないのと、万葉集の時代に木槿が日本に在ったという証拠が乏しい。
(4)昼顔説は、それを裏付ける証拠が乏しい。
(5)山上憶良が生きていた時代から200年ほどたった平安時代に書かれた漢和辞典の「桔梗」の項で、阿佐加保(あさがお)と振り仮名が振られている。
以上の理由で、山上憶良が詠った「朝顔」は「桔梗」であるというのが、正しい説であると牧野博士は説いており、それが正しいとされているのです。
なぜこの歌が取り上げられるようになったの?

歌人であり国文学者の”土屋文明{つちや ぶんめい、1890年(明治23年)~1990年(平成2年)}はこの歌は「普通の記載文であって特に取り上げる程の特色のないもの」という評価をしていました。
ところが土屋文明よりも世代が少し後の万葉学者の第一人者である”伊藤博”{いとう はく、1925年(明治58年)~2003年(平成15年)}は二首目の「また」に注目した。
「萩の花 尾花葛花(くずはな) なでしこの花 おみなえし また 藤袴(ふじばかま) 朝顔の花」
この「また」という言葉は「あだやおろそかに用いられたはずがない」と指摘し、新しい画期的な解釈を発表したのです。
一首目の「指折り(およびをり)」という言葉は子供に呼びかける俗称で「指を折り数えている動作の投影」であること。
「また」とは指を折り数えていき、5本の指になったところで別の手に変えて数える動作であると解釈したのです。
山上憶良の歌から、伊藤博氏が見た世界をまとめると次になります。
伊藤博氏が見た世界
この時代の国主には、自分の配下に属する郡を巡察し、百姓の生活の状態、風俗を観て廻るという任務があった。
この任務を遂行中に見かけた野に遊ぶ子供をを前にして、呼びかけた言葉なのではないか?
そして、この歌はそのときに掛けた言葉を投影する歌であったのではないか?
山上憶良は筑紫の野原で、花をちぎって駆け巡るの子供達を見て、世に言う秋の七草の花の名を教えたくなる気持ちが湧き上がったのではないか。
だとすればこの二首かた伝わるのは、筑紫の秋の光の爽やかに注ぐ野原で駆け巡る子供達を前に、相好を崩しながら秋の七草を指折り数え挙げている好々爺山上憶良の微笑ましい姿を思い浮かべることができる。
この伊藤博の新しい解釈によって、この山上憶良の平凡であった二首に新たなる意味と生命の息吹が生み与えられることになったのです。
山上憶良とは

この二首を詠んだ”山上憶良”のデータをご紹介しておきます。
氏名:山上憶良(やまのうえおおくら)
職:万葉歌人、国主
出自:不明,百済系渡来人説など諸説がある。
経歴:702年遣唐使の随員として渡唐。
帰国後伯耆(ほうき)守→東宮侍講を経て筑前守となり,大宰帥(だざいのそつ)大伴旅人と交遊を深めた。
「万葉集」には長歌11首,短歌68首,旋頭歌(せどうか)1首(作者に異説のあるものを含む)のほか漢詩,漢文の作品もあり,〈貧窮問答歌〉にみられるような思想性・社会性を特色とする。
また和歌の編纂(へんさん)物《類聚歌林》があったというが現存しない。
※ウィキペディアから引用
まとめ

「秋の七草」のあとに、「新秋の七草」が提唱されはじめた。
「秋の七草」よりももっと美しい花はあるではないか!と
その草花は次の七つ。
秋桜(コスモス)、菊、葉鶏頭、彼岸花、白粉花(おしろいばな) 、秋海棠(しゅうかいどう)、赤飯(あかまんま)。
しかし、「新秋の七草」なんて今はほとんど耳にすることもなくなった。
奈良時代から、引き継がれてきた山上憶良の「秋の七草」を楽しむ流れは、今もなお派手さを見せることもなく、静かにこの日本に鎮座している。